「筑波大学の情報学群情報科学類・情報メディア創成学類の編入試験に向けてモチベーションを上げたい!」
「合格するためにはどんな勉強が必要なの?」
「編入試験の当日の様子がしりたい!」
今回は、そんな方に向けて私の体験談を書きました。
ただ私は、この試験で完ぺきな点数をとったわけではないので、参考程度にご覧くださいね。
筑波大学 編入試験 体験談 R5年 情報学群情報メディア創成学類
自己紹介
名前:豆太郎
スペック:TOEIC825点、基本情報技術者
肩書:大学2年生
所属:私立大学文系
趣味:プログラミング、釣り、ランニング
内容
筑波大学の編入試験を受験しようと考えた理由
- 自分の力を試したかったため
- 情報科学、心理学、脳科学の複合分野に興味があり、それら研究活動・授業が充実していたから
しかし筑波大学はとても倍率が高く、そもそも合格することは難しいと考えていました。
ですので、他の大学を2つほど受けましたし、「落ちてもいい。」という心構えで受験しようと思っていました。
勉強の流れ・使った参考書
今回は、英語(TOEIC)以外の、情報、数学でどのような勉強をしていたかを紹介します。
まず私は商業高校出身であるため、はじめの勉強は高校の数学b・Ⅲから始めてました。
高校で理系だった方や高専の方は、9月以降の勉強が参考になるかもしれないです。
2021年
4月下旬~8月
平均4.4時間程度/日

はじめは編入するかどうかの迷いがあったため、サークルやバイトをしながら、勉強をしました。
しかし、7月にTOEIC565点を取ったことで自分に自信がついて編入試験を受けることを決めました。
また、7月にサークルやバイトを思いきって辞めました。
数学
- 放送大学 入門微分積分・入門線型代数←当初は、高校数学の知識もなかったため分かりませんでした。
- 初めから始める数学Ⅲ、数学b(マセマ社)2周
- 黄チャート数学Ⅲ
ここで、高校数学の基礎を固めることで、大学数学の理解が容易になりました。
情報
- 特にない
9月~12月
平均6.2時間/日
(前期間比較+1.4時間)

徐々に、勉強する習慣を身につけていきました。
TOEICも徐々に結果がでてきましたし、9月~12月はイケイケな感じでした。
このときにTOEICでいい点をとって筑波を受けようと決めましたからね!
数学
- 黄チャート数学Ⅲ 2周
- 放送大学 解析入門と線型代数学
- マセマ線形代数学&演習 2周
- マセマ微分積分 1周 ←表面積とイプシロン・デルタ法はやらなくて良かったです。
情報
- 応用情報技術者試験のプログラミングの問題 約10年分
- 競技プログラミング(paiza,atcoder)←競プロはモチベーションと質(アウトプット)の向上に役立つからおすすめです。
2022年
1月~3月
平均5.8時間/日
(前期間比-0.4時間)

2月からTOEICの勉強をやめ、数学と情報が中心の勉強に切り替えました。
数学、情報(プログラミング)といった思考系の科目は、英語のような暗記系の科目よりも集中力を使うため、なかなか長時間勉強することができませんでした。
春休みは勉強する絶好のチャンスなのに、前の期間と比べて一日の勉強時間が30分くらい減りました。
春休みは、かなりモチベーション維持が難しかったです。
ただ、この時期(2月)から専門科目に集中して取り組みはじめたことは正解だったかと思います。
数学
- マセマ微分積分演習 3周
- 編入数学徹底研究 3周(8章、14~18章を除く)
- 過去問(筑波大学、香川大学等)

情報
- c言語によるはじめてのアルゴリズム入門 1周
- 定本cプログラマのためのアルゴリズムとデータ構造 1周
- Atcoder←C言語でやることが試験対策になるのでおすすめです。分からない文法が多かったため、そのつど調べながらやっていました。

Atcoderサイト↓
AtCoder:競技プログラミングコンテストを開催する国内最大のサイト
4月~6月下旬
平均5.5時間/日
(前期間比ー0.3時間)

試験3か月前からは、”勉強時間を増やそう”と思っても、志望理由書や面接対策を行う必要があるため、専門科目の勉強量は落ちました。(筑波大の情報メディア・情報科学の編入試験では志望理由書・面接はありませんが、他の大学の志望理由書や面接対策を3月~始めていました)
志望理由書を書き終わるまでにかなり時間がかかったため、勉強時間が思ったより取れず、あせりました。
とはいえ振り返ると志望理由書の完成を急ぐ必要はありませんでした。
それは途中で志望校に対する考えが変わることがあったからです。
ですので提出直前まで、言葉づかいや志望動機を見つめ直していいものを仕上げることをおすすめします。
完璧な志望理由書を作れば、面接でもスムーズな対応をすることができます。
数学
- 編入数学過去問演習 3周 (3章、6章、1章のC問題は除く)
- 数学/徹底演習(偏微分、重積分、級数、行列の問題以外の線形代数問を2周)
- 過去問(金沢4年分、名古屋1年分、筑波10年分×2回分)

情報
- c言語によるはじめてのアルゴリズム入門 1周
- プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造(1から13章)2周
- 問題解決のためのアルゴリズム×数学が基礎からしっかり身につく本
- Atcoder(アルゴリズムと数学 演習問題集を計60問、競プロ典型☆3以下を20問程度)
東京大学在学中の米田優峻君が書いた本です。↓
問題解決のためのアルゴリズム×数学が基礎からしっかり身につく本
この本とAtcoderと合わせてやることで、編入試験のアルゴリズムの問題が格段に解けるようになります。
C言語によるはじめてのアルゴリズム
c言語の文法を勉強しておかないと難しいですが、編入試験によく出題される問題があります。
プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造
この本は、競技プログラミングの質を高めるために最適です。また、就活で、コード面接をする時に役に立つので、持っていて損はないです。
この時期は、試験科目のプログラミングで必要な数理的な知識を身につけることで、同時に数学の点数も上げることを意識しました。
直前期2週間前
平均7.7時間/日
(前期間比+2.2時間)

試験の2週間前は、とにかくあせっていました。
なぜなら、併願として受験した九州工業大学の数学のできが悪く、自信をなくしたからです。
そして、大学数学の基礎問題を徹底的にやることにこだわりました。
結果的に、筑波大学を受験する前に九州工業大学に合格したことが分かったので安心して受験することはできました。
数学
・教科書(線形空間、陰関数、テイラー展開を読み込みました)
・編入数学徹底研究1周←とにかく、忘れかけていた基礎を叩き込みました
・過去問(筑波10年分×1周)←A3用紙に罫線を付けたものをローソンでプリントして、本番に近い形で解きました。おかげで試験での罫線付きの答案用紙に驚くことなく、できました
情報
・過去問(筑波10年分×1回)
・定本Cデータ構造とアルゴリズム
⇑⇑プログラミング問題の長文対策のため、この本で読解力を身につけることをお勧めします。

ー-------------------
受験年の前のとしの4月下旬からの約15か月間にわたるstudyplusの記録によると試験科目(TOEIC、情報、数学)を合わせて約2600時間(月平均約170時間)勉強をしました。
おそらく、私のように、一から勉強すれば、一般入試とさほど変わらないくらいの勉強量が必要かと思います。
しかし、高校受験で英語・数学をある程度勉強していた方なら、もっと少ない勉強時間で対策できると思います。
試験前日・当日
秋葉原駅からつくばエクスプレスでつくば駅に前日5時に到着しました。ホテルは、筑波駅近くのダイワロイネットホテルに宿泊しました。
このホテルは、試験場に近いので受験生にとても人気です。ですので、2か月前の予約をお勧めします。(私は、1か月前に予約をして、”あと数席”と言われました)
そして、ホテルの到着後、試験場の下見をしました。

そして、試験場近くの魚定食屋で食事を済ませ、前日は疲れない適度に勉強することを意識して、
編入数学徹底研究の
- 重積分、
- ベクトル空間
- 2変数極値
の問題から10問程度解き、11時半に寝ました。
当日の朝は、7時に起き、その後、ホテルの朝食を食べました。
朝食後は、試験で出そうな問題を5問程度解き、9時に試験場に向かいました。
試験本番
試験は、私がいた教室は40人程度でした。試験15分前にTOEICのスコアシートの回収があります。
その後、答案用紙と下書き用紙、問題用紙が配られます。
答案用紙と下書き用紙は、ホッチキスで止めてあります。
そしてこの答案用紙と下書き用紙は罫線が入っているので、いつもの空白の紙と違って、不便さを感じる方もいるかもしれません。

試験開始3分前くらいに、答案用紙に名前、志望学類、受験番号を書く時間が与えられますが、ホッチキスを外したり、名前を書いたりするのにかなり時間がかかります。
ちなみに、開始時間内に作業をできていない人が数人いたのですが、開始時間を1分繰り上げてもらえたので、焦らずに作業をしましょう。
試験内容は、数学2問・情報2問でした。
私の自己採点の結果は以下のとおりです。
数学1 5割
数学2 9割(計算ミスがないなら、10割)
情報3 8割
情報4 1割
過去問と比べて、かなり出題傾向が変わって難化していたと思います。
とくに、情報の2問の問題文の量がかなり多くなったと思います。
ですので、アルゴリズムの基礎を覚えるだけでなく、長い文章を読み、プログラムを理解するといった勉強をする必要があるかもしれません。
ハフマン符号化が出題されていたこともあり、基本情報・応用情報技術者試験のプログラミングの問題に似ているなと個人的に思いました。
試験後
試験後、本来得点を稼ぐはずだったプログラミングのできがあまりにも悪かったため、不合格だと思いました。
けっこう、悔しかったです。
ただ私にとって筑波大学が最後の試験だったので、「ここまでよく頑張った!」という達成感や解放感もありました。
帰りは筑波大学のきれいに整備された歩道を通り、つくば駅付近の店でひとりで食事をして帰りました。

それから12日後、合格発表の日が来ました。
もちろん、不合格であると思っていたため、特に緊張もなく、午前10時前に起き、ホームページを開きました。
情報メディア創成学類に自分の受験番号がありました。
信じられなかったため、何度も実際の受験番号とホームページの受験番号を見返しました。
「受かった、、、、!!」
ただ、私が受かった?という疑問も少しありながらも、これまでにない嬉しさを感じました。
アドバイス
筑波大学の試験について
今回の試験は、おそらく過去最多の227人の志願者で倍率は、約7倍でした。
その影響か、試験もかなり難化していました。
今後も例年の出題通りにいかない場合もあるため、過去問だけでなく、競技プログラミングや資格試験(特に基本情報の情報理論)など、幅広い知識を身につけることをお勧めします。
また、筑波大学の試験は志願者、問題ともにイレギュラーなため、自分の力を発揮できず、不合格になる可能性は大いにあります。
ですので、複数の大学を併願することをお勧めします。(私は、九州工業大学と岩手県立大学を併願しました。)
試験当日のアドバイス
私は、おそらく合格最低点に近い点で受かったかと思います。
今でも、試験の最後まであきらめずにやって、終盤で情報の問題を解くことができて、良かったと思います。
ですので、難しい問題が出ても、あきらめずに挑戦してください。そうすることで少しでも合格する可能性は上がります。
これから編入試験を目指す方へ
編入試験は、TOEICや専門科目が出題され、どのみち将来に役立つであろう勉強をすることができます。
ですので、試験の合否に関わらず、編入試験にチャレンジしてみる価値はあるかと思います。
そして、私の勉強記録を見てもらえば、わかる通りに、コツコツと勉強を積み重ねることが大事かと思います。

1年間ちょっと勉強すれば、気づけば、複数の国立大学に受かる学力が身についています。
ですので、今、編入試験に受からないと思っている方でも、毎日勉強を継続すれば、必ず成果は出てきます。それを信じて、コツコツと頑張りましょう。

また、以下の記事は私が実際に筑波大学に入学してからの内容(続編)も書きました(2023年12月更新)。また、どのような人が大学編入するべきかを書きました。大学編入しようか悩むって人はぜひ見てください。↓
そして、編入試験について不安に思っていることがある方は、以下のページを確認ください。
また、編入試験は、TOEICの勉強が一番大事です。
編入試験までの日数は、365日、180日、100日と気づかぬうちにどんどんなくなっています。
ですので、一日一日を大事に過ごしましょう。
そして、TOEICをより短期間で、高得点を取りたい方は、以下をお勧めします。
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISHスタディサプリ パーソナルコーチプラン
自分のレベルに合った指導と学習計画で短期間でTOEICの点数を向上させることができます。
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISHまた、今なら7日間無料でサービスを体験できるので、ぜひ試してみてください。
以上、合格体験記でした。
以下におすすめの記事を紹介します。大学編入を受けるつもりだけど、難易度が分からなくて不安な人にぜひおすすめです。私もどのくらいのレベルか分からずに、不安でモチベーションが湧かない時がありました。しかし、結果的に複数の大学に合格できました。以下の記事を参考に、大学編入は受かることができるということを知ってもらい、モチベーションを高めてください。
/





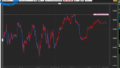

コメント